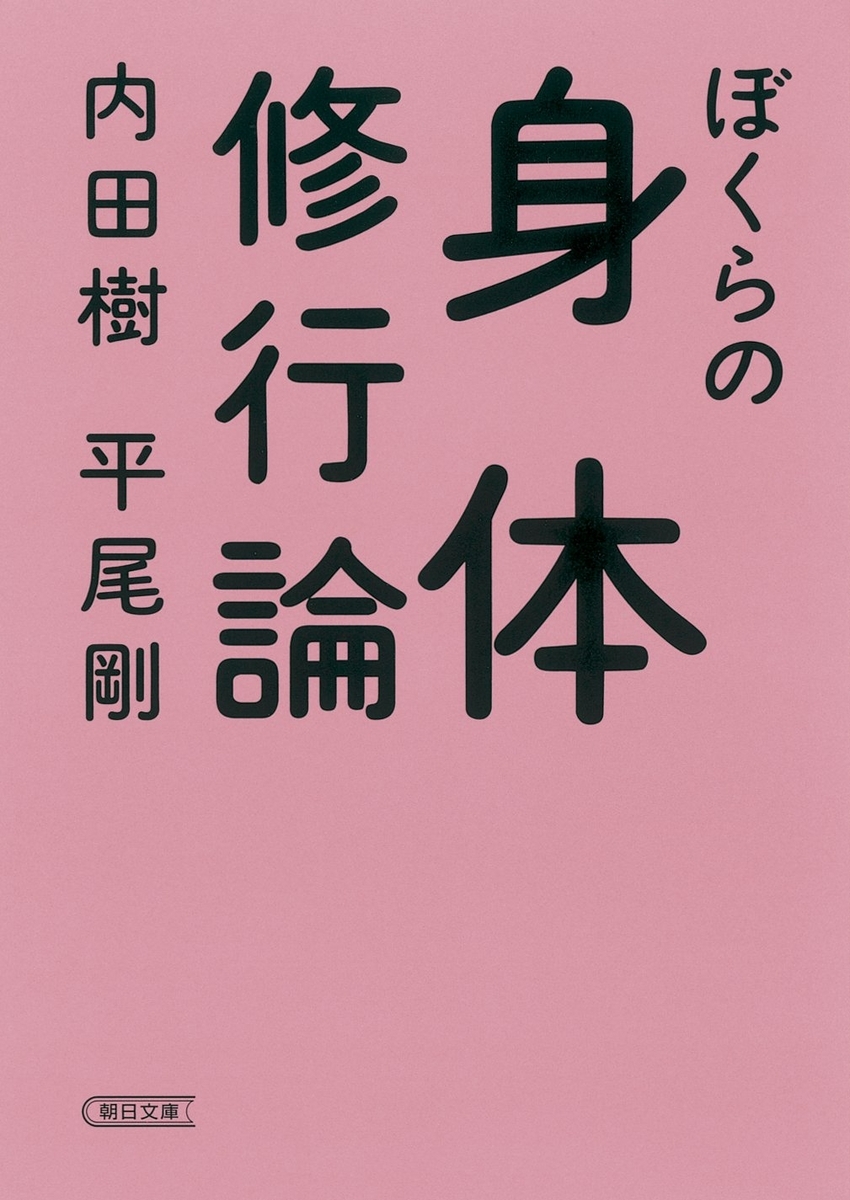 ≪内容≫
≪内容≫
思想家にして武道家のウチダ先生と元ラグビー日本代表の平尾剛氏が身体論をめぐって意気投合。スポーツ嫌いの子どもが増える理由、筋トレの有効性、勝敗や数値では測れないカラダの魅力と潜在力について語り尽くす。文庫版オリジナルの特別対談「進化する身体論」収録。
私、運動が大嫌いです。
だけど身体を動かすことが嫌いなのではなくて、一人で水泳したり走ったり、youtubeのダンスエクササイズとかヨガとかするのは好きなのです。
じゃあなんで運動が大嫌いなのかというと、軽い呪いのようなものがかかっているからだと思っています。
学生時代の「わ~運動神経ないね!」とか「走るの遅っ!」とか、そういう他人からの悪意のないただの感想みたいな言葉や、自分自身が他人と比べて劣っていると実感してきた経験によって、私=運動出来ない=運動嫌いという揺るぎない自信みたいなものが出来ています。
だけど、一人で動いて汗をかくのが好きならば、運動自体は好きなのかも知れない。
他人と比べるのではなくて、自分だけの感覚とするなら。
本書は運動についてもですが、それより身体について語られています。
すごくそうなんだよな~って思ったし、励まされたり、何より「私、運動が好きかも!」と思えてきたので、身体に興味がある人はとても楽しく読めるのではないかな、と思います!
気持ちが悪いは大事な感覚

あまりに長い間不自然な身体運用をしてきてしまうと、それに違和感を覚えないようにになる。痛みやこわばりや詰まりが「あるけど、感じない」鈍感な身体になってしまっている。
スポーツの根性主義はだから危険なんです。
「気持ちが悪い」「いやだ」という生物の本性に根ざしている感覚を、身体的な苦痛に対して鈍感になることによって乗り切ろうとする。
これは身体に限らず、人間関係での快、不快も生き延びるための選択をしていると内田さんは書いています。
気持ち悪い状態を打破しようとする動きは最少エネルギーかつ最短距離だそうです。
確かに熱いものに触れたときとか尋常じゃない速さで手が動きますよね。あれ?私こんなに俊敏だったかしら?みたいな。
ここでも書きましたが、スポーツに限らず、努力や根性主義が私は嫌いです。
努力や根性っていう相対的な見方を信じて生きるってことは個として生きていないということと等しいと思うからです。
何事もそうだと思いますが、100人のうち98人が楽しくても残り2人は一切の楽しさも見いだせない遊びやらイベントやらテーマパークだってあるわけじゃないですか。
その2人はなぜ自分が楽しめないのかさえ分からないけれど、なぜか楽しめないという状況も大いにあると思います。
なんか分からないけどいやだ、なんかいやだ、なんか気持ち悪い、なんかこの人いやだ・・・そういう感情って個として生きるからこそ生まれると私は思っています。
そしてこの感情が私は結構強いです。
そしてこういう「なんか分からないけどいやだ」みたいなことを他人に言うと「わがままじゃね?」みたいな感じになることもたくさんあります。
なので、大好きな人はずっと大好きだけど、合わない人はほんとうに合わない・・・という両極端な世界になってしまいます。
だから白黒つけたがるってよく言われるんだろうな・・・と思うのですが、だってグレーでいるのがキモチワルイんだもの・・・と思ったり・・・反省したり・・・。
でも生きていく上で万人となんか上手くいかなくたってそこまで重大なことでもないかなって最近は思うようになりました。
それより、いやなのに頷く方が自分の身体に不調や痛みとして出るから、他人を大事にするより自分を大事にしようと思いました。
快・不快、美味しい・美味しくない、楽しい・楽しくない・・・そういうものをその場の雰囲気や付き合いで選んでいたら、どんどん鈍感になって自分ってものがなくなってしまうと思う。
それを「でも人間関係を円滑にするために必要」とか「コミュニケーションとして」とか「人を傷付けないため」に必要なのだと言われたこともあって、それをそうなのかな・・・とずっと考えてきたのですが、自分にはこの必要性が分かりませんでした。
分からないことで、自分は人間関係を円滑に出来ていないのか、コミュニケーション能力がないのか、人を傷付けてきたのか・・・と気にかかっていたのですが、本書を読んでそれはまた違うなって思えました。
一流のアスリートとは

ありがたいことに、気持ちのいい身体運用をしているひとって発信力が強いから、子どもにもそれは分かる。
「今このひとすごく気持ちよくなってる」というのがわかる。
そういうオーラを出せるのが一流のアスリートだと思うんです。
すごくそう思う。
人に合わせている人って全然本意が見えないんですよ。
まぁ人に合わせているから当たり前なのかもしれないのですが、そうなってくると本当にその人が楽しいと思っていたとしても相手に伝わらなくなってしまうと思うんです。
あるけど感じない鈍感な身体と、本意を見せない表情になっていくのは同じな気がするんです。
本人は「本当に楽しい!」と思っていても、その楽しいが個としてなのか相対的になのか本人にも分らなくなってしまっている状態。
本人が分からないものは他人にも伝わらないことの方が多いと思います。
私は「伝えたい」という感情が強いんだろうなぁと思っています。
だから一個の記事が長いし、ブログやってるんだろうなと思います。
誰かに「伝えたい」「分かってほしい」という感情があって、それを相手に投げかける為には、自分の身体や表情が素直でなければ相手に伝わりにくいと思っています。
自分を偽ったり隠したりしているのに相手に分かってほしい、というのは相手への比重が大きすぎると思います。
なので、私が「でも人間関係を円滑にするために必要」とか「コミュニケーションとして」とか「人を傷付けないため」に快・不快、美味しい・美味しくない、楽しい・楽しくないを相対的に選べないのは、自分の気持ちを「伝えたい」「分かってほしい」という気持ちの方が強いからなんだって思いました。
私は気持ち良さそう・・・という人はあまり社会で見ませんけど、無理していなさそうで自然な人に惹かれます。
この本を読んでいると、もっと自分のことを知りたくなって自分の身体が今どんな状態なのか知りたくなってきます。
自分のことなのに、まだ全然知らないことがあるって何だか不思議です。
だけど、今の私は絶対に気持ちのいい身体運用はしていないと思うのです。もっと身体的な快・不快に敏感になりたいな、と思いました。
本書を読むと、自分に向き合いたくてたまらなくなる。
出来ないから、楽しい。

