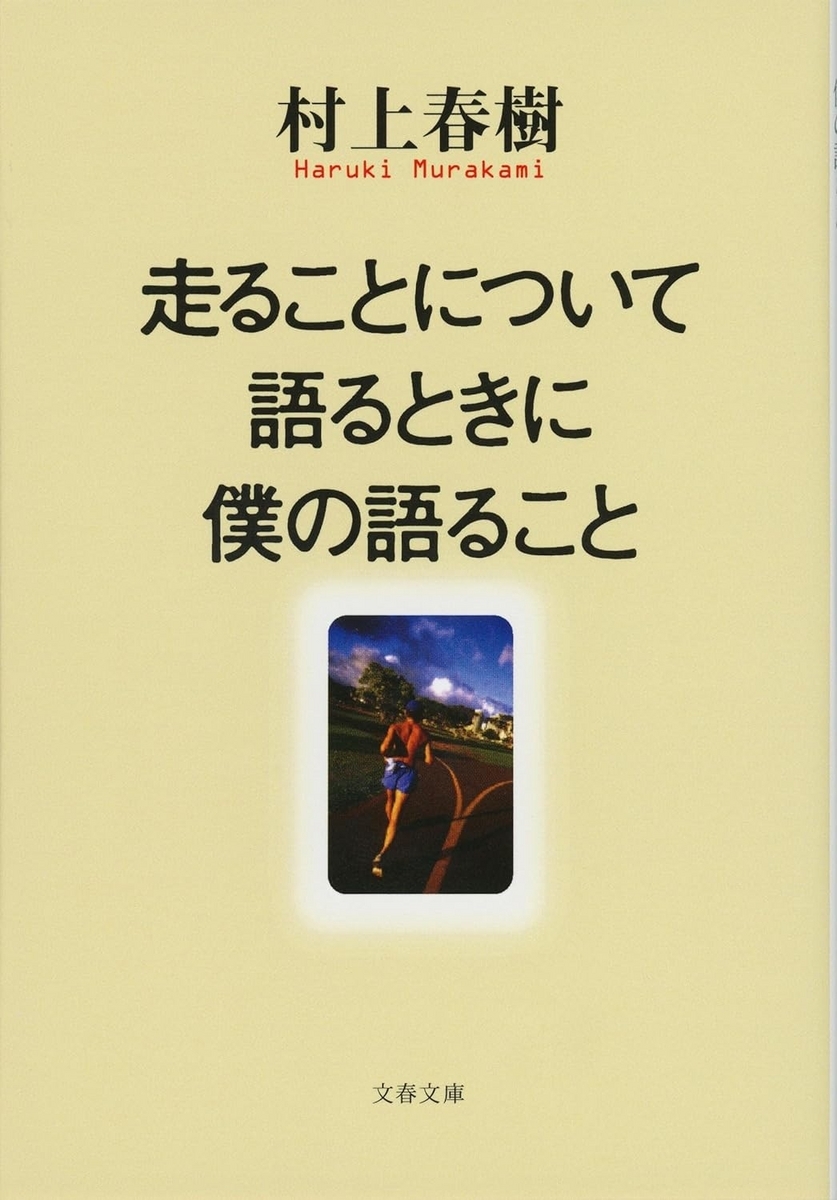 ≪内容≫
≪内容≫
もし僕の墓碑銘なんてものがあるとしたら、“少なくとも最後まで歩かなかった”と刻んでもらいたい―1982年の秋、専業作家としての生活を開始したとき路上を走り始め、以来、今にいたるまで世界各地でフル・マラソンやトライアスロン・レースを走り続けてきた。村上春樹が「走る小説家」として自分自身について真正面から綴る。
めっちゃ笑いましたw
今日は走りたくない、なんか言い訳考えよう・・・とか、こんな朝早く走るのなんか嫌だけど、他の人は満員電車に乗って通勤し会議してっていう一日なんだ、そう思えば朝走るのなんかまだマシじゃないか・・・とかw
小説家というか、一人の人間が自分と向き合った話という感じです。
僕が僕であって、誰か別の人間でないことは、僕にとってのひとつの重要な資産なのだ。

誰かに故のない(と少なくとも僕には思える)非難を受けたとき、あるいは当然受け入れてもらえると期待していた誰かに受け入れてもらえなかったようなとき、僕はいつもより少しだけ長い距離を走る事にしている。
いつもより長い距離を走ることによって、そのぶん自分を肉体的に消耗させる。そして自分が能力に限りのある、弱い人間だということをあらためて認識する。いちばん底の部分でフィジカルに認識する。
そしていつもより長い距離を走ったぶん、結果的には自分の肉体を、ほんのわずかではあるけれども強化したことになる。
腹が立ったらそのぶん自分にあたればいい。悔しい思いをしたらそのぶん自分を磨けばいい。
そう考えて生きてきた。
黙って呑み込めるものは、そっくりそのまま自分の中に呑み込み、それを(できるだけ姿かたちを大きく変えて)小説という容物の中に、物語の一部として放出するようにつとめてきた。
悔しくて眠れないとき、悲しくて何も手につかないとき、無心に泳ぎ続けたり走り続けたりすると、どんなに心は興奮していても体力の消耗によって、すとん、と眠ってしまう。
生きていて理不尽な目に遭わない人はいないと思う。
根拠なくいじめられたり、根も葉もない噂を立てられたり、言ってもいないことを問いただされたりすることって誰しもがあると思う。
そこで「自分が悪いんだ」と落ち込んだり「相手が間違ってる!」って相手を変えようとしても、起きてしまったことはどうにもできない。
村上春樹は、どうしようもなくたって自分はこれで生きていくしかないのだと言っています。嫌いなところ、コンプレックス、弱い部分、そういうものひっくるめて自分なんだし、自分の生まれ持った性格は変えられない、と。
心を守るために、肉体を自ら鍛えることは不可欠なのだ。
正気を失った人間の抱く幻想ほど美しいものは、現実世界のどこにも存在しない。

水が飲みたい、でもここで立ち止まって水を飲んだりしたら、そのまま走れなくなってしまうような気がする。 喉は渇く。しかし水を飲むのに必要なエネルギーさえ残ってはいない。
そう思うとだんだん腹が立ち始める。
道路脇の空地に散らばって幸せそうに草を食べている羊たちにも、車の中からカメラのシャッターを切り続ける写真家に対しても腹が立ち始める。
シャッターの音が大きすぎる。
羊の数が多すぎる。
(中略)
「あと2キロですよ。がんばって」と車から編集者が明るく声をかける。
「口で言うのは簡単なんだよな」と言い返したいのだが、思うだけで声にならない。
余裕がないときって、なんだか無性に腹が立ちますよね。
羊の数が多すぎるとか面白くてしょうがないけど、実際自分が走ってたらそう思うだろうし、太陽が熱すぎるとか地面が固すぎるとか、もっとしょうもないことにも腹が立ちそう。笑
走っている間に想像していたビールは完走後に飲むと想像ほどおいしくなかったらしく、そこから「正気を失った人間の抱く幻想ほど美しいものは、現実世界のどこにも存在しない。」に繋がっています。
小説家のこういう表現は、小説だけに力を入れているからじゃなくて走ることにも全力で取り組んでいるから生まれたんだなぁって思いました。
小説以外の何か、どこかでこういう思いをしなきゃ正気を失った人間の想像がどんなに美化されているかなんて解りませんよね。
先日の「思考の整理学」で学んだこと、一つでは多すぎるっていうのがまさにこういうことかなって思います。
書くことひとつに絞ったら奪われていたかもしれない。
書くこと以外にもあるから、小説家としての自分が生きてくる。
思考の整理学→理論
走ることについて~→実践した記録
なので一緒に読むと効果が分かって面白いかもしれません。
真に不健康なものを扱うためには、人はできるだけ健康でなくてはならない。

我々が小説を書こうとするとき、つまり文章を用いて物語を立ち上げようとするときには、人間の存在の根本にある毒素のようなものが、否応なく抽出されて表に出てくる。
作家は多かれ少なかれその毒素と正面から向かい合い、危険を承知の上で手際よく処理していかなくてはならない。
そのような毒素の介在なしには、真の意味での創造行為をおこなうことはできないからだ。
ランナーというか運動している人は健康的なイメージがある。
村上春樹は小説家なので、健康になっちゃったら小説書けなくなっちゃうんじゃないの?とときどき人に言われるそうです。
確かに、小説家って家でもくもくと机に(もしくはパソコン)向かっているイメージだし人柄も明るいよりちょっと暗そうなイメージ。
小説家と健康はなんだか正反対な気もするが、村上春樹は不健康なもの(もしくは毒という危険物)を処理するためにはそれなりの免疫をつけるべきだと言います。
毒に侵されて死なないための体力をつけるということですね。
私はここのところで「健全な魂は健全な肉体に宿る!!」というソウルイーターの言葉を思い出しました。
想像力に負けないくらいのフィジカルが必要というのは、私にとって初めて聞く考えであると同時に「なるほど!!!!」と「教えてくれてありがとう!!」という気持ちになりました。
真に不健康なものって、私たちの身近にありますよね。
例えば家族の仲が上手くいっていないとか、会社がブラックとか、借金とか、いじめとか・・・個人差はあれど、全てが健康な状態っていうのはほぼないような気がします。
些細なことでも心のどこかに引っかかりがあるのではないでしょうか。
そんなとき、身体も弱かったら。
「全くあんたはダメな嫁で!うんたらかんたら・・・」とか言われた矢先にインフルエンザにかかったら「私って本当にダメな人間かもしれない・・・」とか弱気になりますよね。
ただでさえ、身体の不調はメンタルに影響してきます。
ということは、メンタルの不調も身体に影響してくるのです。
身体と心、健康と不健康は表裏一体です。
自ら進んで不健康に立ち向かおうとしたら健康に目を向けるのは理にかなっていることだなぁと思いました。
健康な自信と不健康な慢心を隔てる壁はとても薄い。
健康と不健康。
生きていく上で一番重要なバランスなんじゃないでしょうか。
私は小説家でもランナーでもないけれど、本書を読んで新しい視点が出来た気がしました。
あの村上春樹でも、めっちゃ水泳の特訓したのに本番で過呼吸になって泳げなくなっちゃったり、ランニング中にかわいいお姉さんがいたから続けられたとか言ってたりして、あ・・・普通の私と同じ、普通の人じゃん!って思って楽しかったです。
私が一番共感したところ
文章というホームグラウンドでは、僕はそれなりに自在に有効に言葉と文脈をキャッチし、かたちに換えていくことができるーなにしろそれが仕事だから。
しかしそのようにしてつかみ取られたはずのものを、人前で実際に声に出して語ってみると、そこから何かが(何か重要なものが)こぼれ落ちていくという切実な感覚がある。
知名度がすごいのでなんだか特殊な人かと思っていましたが、地道にひたすら努力を続ける人間の話です。
かっこいい大人の話。


