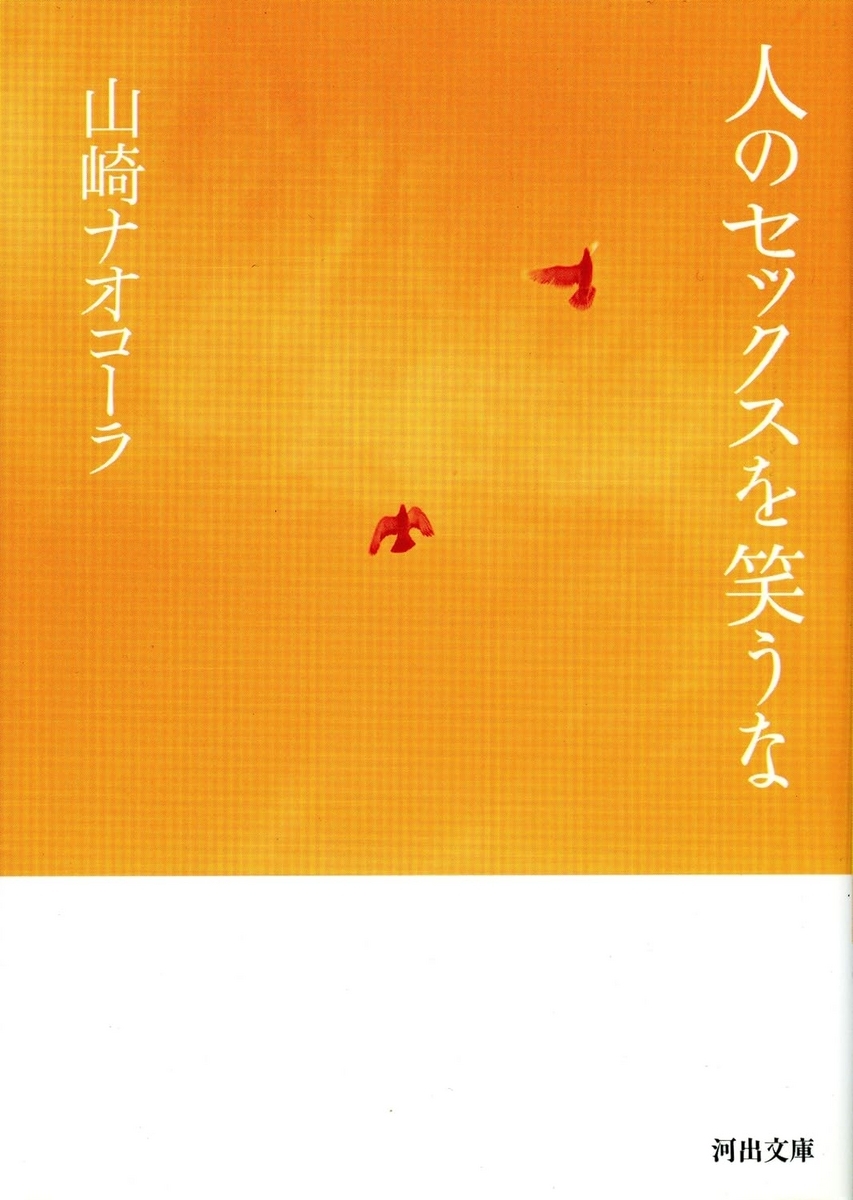 ≪内容≫
≪内容≫
19歳のオレと39歳のユリ。恋とも愛ともつかぬいとしさが、オレを駆り立てた——「思わず嫉妬したくなる程の才能」と選考委員に絶賛された、せつなさ100%の恋愛小説。第四一回文藝賞受賞作。
セックスって文学の中ではたくさんの意味があるんだろうな、と最近思います。
ただ単に性交ではなくて、それは何かの暗示だったり予感だったり、その先に向かう道しるべだったり。
この本は解説にすごく助けられました。
解説の必要性というものを初めて感じたかもしれません。
そもそも解説の必要性について考えたことがなかった。
刺激的な内容じゃなくて、淡々としています。
呆気なく始まり、呆気なく終わる。
静かに燃えて、消えるのも静かにゆっくりと。
じわじわと。
読後じわじわとくる作品。
映画版感想記事↓
恋の形に好みなどない

オレはかわいい女の子が好きだと思っていた。
例えば自分には、顔に好みがあると思っていた。昔の加賀まりこのような、黒猫みたいな女の子がいいな、生意気そうな目や、ぷくっとした唇の子、そんな子が現れねえかな、と考えていた。
ユリはまったくそんな顔はしていない。
目は一重で、顔は丸顔。薄い唇はいつもカサカサ。体には肉が付きすぎている。疲れた顔をしていることも多い。
しかし恋してみると、形に好みなどないことがわかる。好きになると、その形に心が食い込む。
そういうことだ。
オレのファンタジーにぴったりな形がある訳ではない。そこにある形にオレの心が食い込むのだ。
最近すごくギョっとした広告がありました。
それは夏に向けて男性も脱毛しよう!という広告で、電車の中で見ました。
世の中はどんどん自然を悪しきものにしようとしている。
脱毛、脱臭、整形、黒眼を大きくするコンタクトレンズや、ヘアエクステ、まつげエクステ・・・。
自然のものを永久に破棄して、人工のものをつける。
私はきっとこうした方が男性ウケはいいだろうし、世間的にもオシャレで美人で流行りに乗っていて「美しい」に近づけるんだろうな、と思っていました。
だけど、思っていても心のどこかに違和感がありました。
それは「可愛くなきゃ愛してくれないの?」とか「毛の処理が甘かったら嫌われるの?」とかいうことじゃなくて、人が人を好きになったり、好意を抱くのってそこかな?という気持ちがあって、何だか、自分で自分の生理現象とかを捨ててしまったら、自分から「ありのままの私じゃなくて作った私を見て」って言ってるような気がしたのです。
脱毛は別に異性のためじゃなくて、自分の手間を省く目的だったり、清潔さを保つためだったり、という考えもあると思うし、整形だってそれがやりたいことならいいのかな?と思います。
思うのは、世の中の「男性が女性に対してホントに思っていること」だったり「女性が男性にしてほしいこと」というのは、商業作戦なんじゃないかなってことです。
大袈裟に言うと世の中の女性たちの大半が脱毛していなくなったから、今度は男性も囃したてて脱毛に来させよう!みたいな。
結果的にそれでモテる人もいるかもしれない。だから一概にいい悪いとしたいのではなくて、人工的なもので象った自分や心で恋愛したら、それはやっぱり自然な恋じゃなくて、人工的な恋だと思ったのです。
恋は自然現象だと、生理現象だと言うのは無理があって、自然に恋をしたいなら自分の求めた形にハマる人を見つけるのではなくて、そこにある形に自分がハマっていくことなんだろうな、と。
私はそれを恋だと呼びたい。
人の数だけ色んな恋がある

「会えなければ終わるなんて、そんなものじゃないだろう」
花火の火は気まぐれに色を変えながら、違う花火に移り続けていく。
人のセックスを笑うなってどういう意味なんだろう?って思っていたんですが、たぶんセックスのハウツーではなくて、恋愛のことなんだろうな、と思いました。
年齢の差やら同性同士やら何やら曰く有り気なカップルやら、色んなパターンがあって。
人は"普通"じゃない恋愛を非難するけれど、それらを侮辱する権利は誰にもない。
恋は終わっては始まり、始まっては終わる。
その内終わらない恋が愛に変わるときが来るかもしれない。
二人の間での恋は終わりを告げるけど、未来はないかもしれないけど、それでもその時恋をしていた二人の記憶はずっと残る。
会えなければ忘れてしまうような、消えてしまうような気持ちなら、恋と呼ばない。とでも言っているような主人公の言葉がすごく胸に沁みました。
それは未練とかまだ好きとか、そういう気持ちを超えて、一つ一つの恋を大切にしてきた証のように感じました。
解説より

思えば、言葉は男性のものであり、感覚は女性のものであるとされてきた。だが、感覚が男性のものであって悪いのか(逆にいうなら、言葉が女性のものであって悪いのか)。
(中略)
「男性中心社会」への反撃としての「女性言葉」の奪還が、その本質において攻撃的であるとするなら、女性化しつつある男性を肯定するこの小説は、その本質において攻撃性を持たない。
言葉は男性のものであり、感覚は女性のものであるとされてきた。とか知らなかったので勉強になります。
私は読書は好きですが、読書の歴史というか文豪たちの戦いに関して無知です。
数少ない知っていることは、蟹工船の作者小林多喜二が命をかけて労働階級の人々の真実を小説にしたこと、くらいです。
女生徒/皮膚と心/葉桜と魔笛/太宰治での太宰治は女性でした。
私は「よく女性の気持ちが分かるなぁ」くらいしか思っていなかったのですが、本書の解説によると彼は大きな言語の変革期に出現しており、新しい言葉を使おうとしたからだ、と書かれていました。
女性作家が男性視点で書く小説は動かないで/マルガレット・マッツアンティーニで読んでいたので特に驚きはなかったのですが、言われてみると他に心当たり・・・ないかも。
文学に歴史があることは重々承知ですが、あぁ全然私って知らないのね・・・・と痛感しました。
もし、この解説がなかったら本書への理解はかなり薄れていた気がします。
静かで淡々と、ただ年上のユリを受け入れる青年が何を表現していたのか、それを教えてくれた解説。
ほんと助かります!!!
最後に「虫歯と優しさ」より、すごく好きな一文。
私は、伊東さんのことを、頭が良かったり、面白かったりするから、好きだったんじゃないよ。冷蔵庫にハミガキ粉を入れているところが、本当に好きだったんだよ
あなたにしかない個性を好きになりたいから、個性を世間に奪われないでほしいと思う。


