 ≪内容≫
≪内容≫
「村上春樹」は小説家としてどう歩んで来たか―作家デビューから現在までの軌跡、長編小説の書き方や文章を書き続ける姿勢などを、著者自身が豊富な具体例とエピソードを交えて語り尽くす。文学賞についてオリジナリティーとは何か、学校について、海外で翻訳されること、河合隼雄氏との出会い…読者の心の壁に新しい窓を開け、新鮮な空気を吹き込んできた作家の稀有な一冊。
村上春樹は有名ですよね。
有名ゆえなのか、嫌いな人もたくさんいます。
amazonのレビューとか。
もちろん好き嫌いがあるので、へえくらいにしか思ってなかったんですが(自分のことでもないし)本書を読むと、村上さん自身が知人に「あれくらい俺にも書ける」とか言われたり、自分で少なからざる数のある種の人々を苛立たせるのは生まれつきの資質のようです、とか言ったりして、相当傷付けられてきたのかな・・・と哀しくなりました。
岡本太郎と村上春樹

自分の中に毒を持て―あなたは“常識人間"を捨てられるか (青春文庫)
- 作者: 岡本太郎
- 出版社/メーカー: 青春出版社
- 発売日: 1993/08/01
- メディア: 文庫
- 購入: 58人 クリック: 968回
- この商品を含むブログ (251件) を見る
私は岡本太郎の思想が大好きで、かなり影響を受けました。
音楽ではhide、哲学では岡本太郎です。
この本の中ですごく感銘を受けたのが、人生の中で経験を積み重ねていくのではなく、それをどんどん削ぎ落して行くんだというような言葉でした。
それをまさに本書で村上春樹も言っていました。
自分のオリジナルの文体なり話法なりを見つけ出すには、まず出発点として「自分に何かを加算していく」よりはむしろ、「自分から何かをマイナスにしていく」という作業が必要とされるみたいです。
考えてみれば、僕らは生きていく過程であまりに多くのものごとを抱え込んでしまっているようです。情報過多というか、荷物が多すぎるというか、与えられた細かい選択肢があまりに多すぎて、自己表現みたいなことをしようと試みるとき、それらのコンテンツがしばしばクラッシュを起こし、時としてエンジン・ストールみたいな状態に陥ってしまいます。
この部分でも、村上さんほんとうに親切だなぁと感じます。
考えてみれば~のくだりを文体にしない人って多いと思うんですよ。もしくはもっと抽象的な言葉で書かれている。
こういう風に分かりやすく、「こういう事ですよ、分かりますか?」と言っているようで、そういうところも好きだなぁと思います。
今更ですが、岡本太郎も日本では当初受け入れられませんでした。
そういった流れに逆らうという点でも二人には共通点があるように思います。
マイナスにしていく作業というのは言うほど簡単ではなく、削ぎ落とした先にあるのは真っ裸の自分自身だと思うので、それ以上に強いものはなくて、それほど自身を曝け出せりものもないと思うんです。
自分がどれだけ赤裸々に話していると思っていようが、明け透けな性格だと自己分析しようが、それは決まった型の中ではそうであるということでしかなくて、まるっきり裸というわけではないんだろうと思いました。
人は、自分と違うもの、理解できないものに対して恐怖を抱きます。
だから攻撃するのです。
皆がそれぞれの服を着て、ルールに従って生きているのに、いきなり素っ裸の人間が来たら「なんじゃおまえは!」となりますよね。
相手はただ服を着てないだけなんですが、やたらめったら服を着せようとします。それは服を着るのが正しいと思っているからです。
逆に言うと裸という発想がなかったことになりますね。
まぁこれは極端な例ですが、やっぱり岡本太郎と村上春樹にはそういう削ぎ落すという気付きがあったんだと思いました。
そして二人が「削ぎ落せばいいんだよ」と教えてくれても、「は~い」と出来るものでもない・・・だからすごいんだよ・・・と思う私なのでした。
一日ずつ着実に

リズムを乱さないように、巡り来る日を一日ずつ堅実にたぐり寄せ、後ろに送っていくしかないのです。そしてそれを黙々と続けていると、あるとき自分の中で「何か」が起こるのです。
でもそれが起こるまでには、ある程度の時間がかかります。あなたはそれを辛抱強く待たなくてはならない。
一日はあくまで一日です。
いっぺんにまとめて二、三日をこなしてしまうわけにはいきません。
One day at a time で一日ずつ着実に、という意味だそうです。
私はこのブログを一日一記事としていますが、当初はたくさん記事が欲しくて、無理矢理一日に複数記事を書いてアップして、二、三日読書する・・・みたいな結局意味があるのかなんなのか分からない状態になっていました。
なので、何とかしようと思い一日一記事と決めたところ、最初は物足りない気持ちがありました。だって一年は365日だから365記事しか年内に作れないんだ、と思うと全く進んでいるような気がしなかったのです。
だけど今では一日一記事というリズムにノレている気がして楽です。いっぺんに進んで行ける人間ももちろんいると思いますが、私はのんびりな方だと思うので、最初に加速したらその分どこかで休まなくては壊れてしまいます。
なので一日一記事、堅実に積み重ねていくことにしました。
たまに、体力もあってバイタリティもある人間に出会い、自分の体力の無さやスピードの遅さに訳も分からず悔しくなるときもありました。
だけど、自分で好きなこととして記事を書いているのに、誰かと比べるなんておかしいじゃないか、と思って自分らしくノロノロでいいんだ、と思うようにしました。
だからこの One day at a time、一日ずつ着実に、はとても好きな言葉です。
ゆっくり確実に生きていく。
それが私に出来ることです。
言葉に宿る力
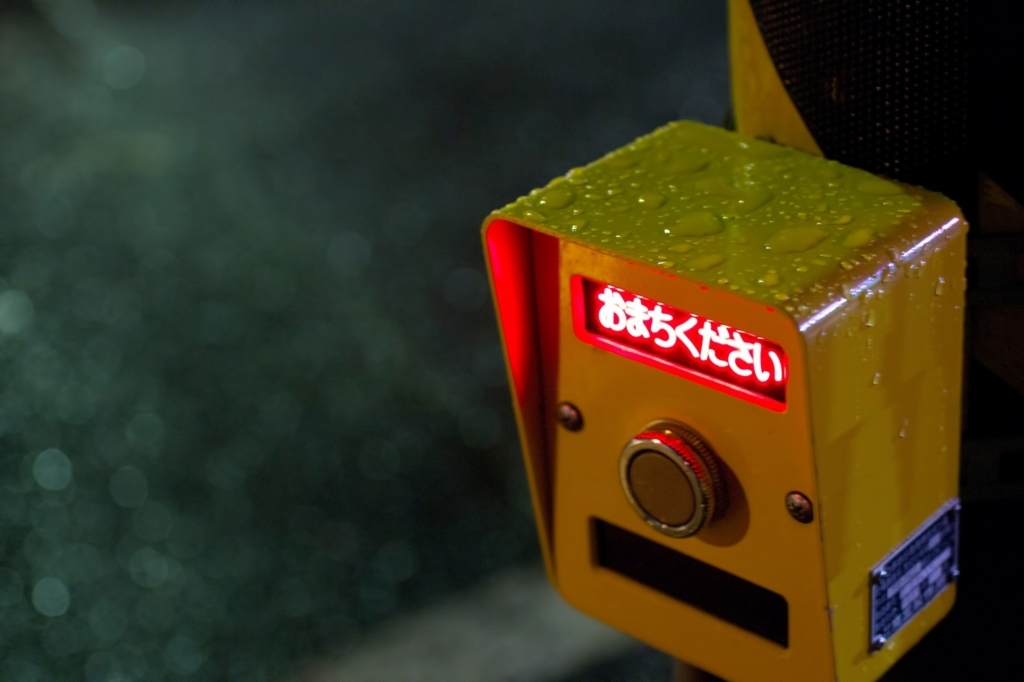
どれだけそこに正しいスローガンがあり、美しいメッセージがあっても、その正しさや美しさを支えきるだけの魂の力が、モラルの力がなければ、すべては空虚な言葉の羅列に過ぎない。
ぼくがそのときに身をもって学んだのは、そして今でも確信し続けているのは、そういうことです。
言葉には確かな力がある。
しかしその力は正しいものでなくてはならない。
少なくとも公正なものでなくてはならない。
言葉が一人歩きをしてしまってはならない。
正しいスローガンや美しいメッセージが、正しい意味を持ったまま生きるためには、それを扱う人間が健全でなくてはならない。
だからこそ、村上さんは肉体の健康に気を使っているんだと思います。
社会の中で生きていくというのは、羊的なことでもあると思っていて、大きな日本という牧場の中で一般市民(羊)は生きていて、それをうまく扇動する国家(牧場主)がいて、さらに市民を統制すべく国家公務員(牧羊犬)がいるような感覚です。
羊たちは不穏な雰囲気や何か違う気がする、というものは感じても、牧羊犬や牧場主の話す言葉にとりあえず従います。
正しいスローガンや美しいメッセージを思い付かない羊たちは、とりあえずそんなものかなぁと思って主に従います。
自分で思い付かないので、何か悪いものを感じても上手く言葉にすることが出来ません。しかも周りには同じような羊たちがいっぱいいるので「まぁいいか」となってしまいます。
もし主が健全ではなく、不健全な魂で言葉を使うなら、その結果は不健全なものにしかなりません。
だからこそ、羊たちはそれが健全なのか不健全なのか見極める力を持とうとしなくてはいけません。
小説や音楽、芸術という影響力のある表現をしようとするなら、その言葉を正しく、健全な魂で扱わなければならない。
健全な魂というのは、私の中では100%自分の意思であるか否かだと思います。
そこに妥協や打診、損得、見返り、そういうものが混じれば、それは不健全へと進んでいくと思います。
本書を読んで思ったのは、やはり村上さんもかなりの読書家であるな、ということでした。そして、やはり風の歌は何もないことを書いていたんだなぁ、ということでした。
何もないことを書こうと思って、ほんとうに何もないって読者に思わせるなんてすごすぎないか・・・と思います。
「イマジネーションとは記憶のことだ。」とジェームス・ジョイスは言った。

