
≪内容≫
美しすぎる少女は大人を狂わせた――。
女流写真家の母アンナ(イザベル・ユペール)は仕事で滅多に家に帰ってこず、母の愛情を求める娘のヴィオレッタ(アナマリア・ヴァルトロメイ)は優しい祖母に育てられながら母の帰りを待つ。ある日、突然帰ってきたアンナは、ヴィオレッタを写真のモデルへと誘う。母親に気に入られたいヴィオレッタはモデルになる事を決心。しかし、アンナの要求は徐々にエスカレートし、大胆なカットを要求される。最初はごく普通のあどけない少女だったが煌びやかな衣装とメイクで次第に大人の女の色香を漂わせ、退廃的な少女に変貌していく・・・
子供は子供らしく。
これが一番当たり前のようで、大切なことのように思う。
子供らしい過去がないまま大人になると、戻れる場所がなくなる気がするから。
写真家とモデルと芸術
突然ですが、タイムリーな写真家とモデルの問題がありましたね。
アラーキー告発で「モデルの弱い立場」浮き彫りに――業界のセクハラ横行が問題視されにくい理由|サイゾーウーマン
kaoriさんのnoteを読んだのですが、なんかありそうな話だな・・・と思いました。
特に「芸術なのに金の話をするな」というあたり。
併せて水原さんの記事も読みましたが、なんか・・・信じたくないですよね。
「おっ今回の撮影ヌードらしいですよ」
「ほうほう」
「よし、今回は我々も見学に行きますか。」
的なノリなんですかね。そんな暇なの?嫌がらせなの?
写真家のママにかまってもらいたくて何が芸術なんだか自分は何が好きなんだか分からないまま、ただママの愛情がほしくてママの言うとおりのポーズ、言うとおりの衣装を着て撮影に挑むヴィオレッタ。
もしも自分が断れば、またママは自分を祖母の元に置いて放浪の旅に出てしまうかもしれない。
正直、絵はすごく美しい。
こういうロリータ個展があったらお金払って観に行きたいとは思う。なんてたって美しいから。この少女役のアナマリアめちゃくちゃ可愛い、きれい、妖艶・・・見ていたくなる存在。
でもさ、子供って存在自体そういうところあると思うんですよね。神聖なものというか、存在自体の美しさというか。
私にはもうすぐ三歳になる姪っ子がいるのですが、特別美人ちゃんってわけではないけれど、色素の薄い細くて柔らかい髪の毛に、真っ白な無傷の肌、紅をひいてなくても赤い唇、大きな黒眼とその周りの青白い強膜・・・いやー子供って天才的に美しい、と思います。
バタイユ的というよりはカント的美しさです。自然の美。
大人になるってそういう自然の美がどんどん社会化されていくので、社会に適応できない人間=異常者=小児愛好家という図式は分からんでもない。
でも、美しく生まれようが、歌の才能を持って生まれようが、それを望んで生まれてきたわけではないんですよね。
母は「私があなたを有名にしてやったのよ」「これは芸術なのよ」と高尚なこと言いますけどね、そんなの知らないよね。
だって、同じ親子だろうがどこに芸術を感じるのか、そもそも芸術に関心があるのかなんて人それぞれじゃないですか。
自分の目で外の世界に出て、相対的に美しいとかこれが欲しいとか、そういう自分だけの価値観ってものを身につける時間が人には絶対に必要だと思うのです。
この時間を与えられないことが、スポイルされる、と同義語な気がする。
それに芸術はセンスだ!と言おうが、金がかかる。
音楽やるってなったら、楽器に機材に、パソコンにソフトにスタジオ代、ライブ代、衣装代・・・ほんっと金がかかる。
画家とかアートだって、お金を稼ぐ時間を制作に回していたら、お金なんて入ってこないんですよ。当たり前だけど、そういう面を見せないのが芸術みたいになってるからその感覚が腑に落ちない人もいると思う。
私は芸術って好きですが、生きることを前提としなきゃ存在しません。生きることを後回しにした芸術はいつか死ぬ。もしくは誰かを殺す。ここで言えば被写体、モデルです。
今の時代はもう生きるのが当たり前になりすぎて、たくさんの人が芸術に流れている気がします。それが悪いことなんじゃなくて、そしたら今度は芸術が当たり前になって、また新たな何かが生まれるか、古い壁紙が見直されるか、になると思うのです。
すごく乱暴に言えば、もう整形しちゃえば誰でも美しくなれるわけじゃないですか。別にお金払って誰かの美しさに昏倒しなくたって、自分を変えちゃえばいい。音楽もお金さえあれば自分で好きなように作れるし、画だって教室に通えるし、アートだって、場所と時間とやる気があればやってみればいい。そういう余裕が現代人にはあるわけだから。
↑こういう華奢な女の子の戯れのシーンが大好きな私なのだった。
芸術はすごい!って言うのはもはや死んでる気がする。だってさ、昔の芸術家とか音楽家とか哲学者ってほとんど金持ちですよ。もしくは金持ちのパトロンがいたんですよ。あとは芸術一家だとかさ。とりあえず自分の生活を担う奴隷なりなんなりがいて、それで自分の時間があったわけじゃないですか。
だから別にその人が辿り着けなくても、後世で誰かが辿り着いていただろうし、トルストイが言うように時代のラベルになっただけっていう感覚が私の中にあります。
私が本当に価値があると思うのは、作品よりもその作者なり製作者なりが「自分がやりたくてやったこと」という前提です。
後々になって「実はやりたくなかった」「実はやらされていた」という事実が発覚した時、私の中ではそれまでの芸術も死にます。
私は荒木さんの写真を見た事もないから、kaoriさんのことも水原さんの広告のことも知らなかったけど、これから先も進んでみることはないだろうと思う。



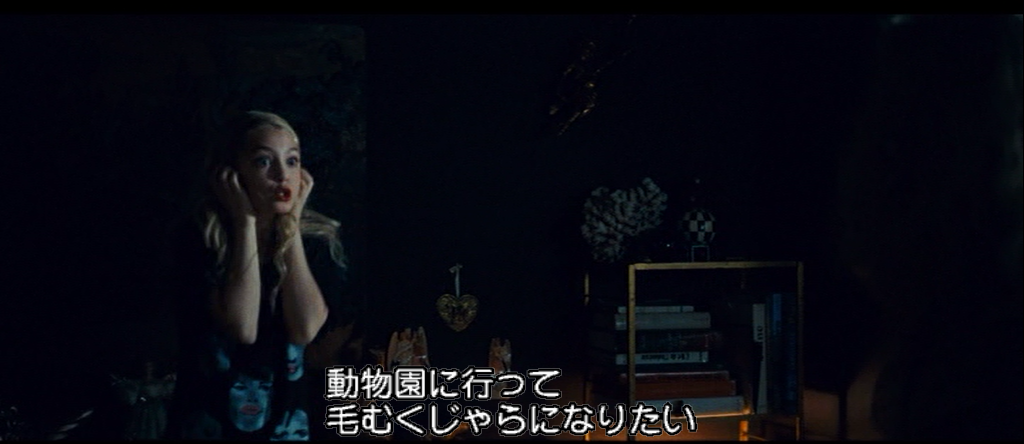


![ヴィオレッタ [DVD] ヴィオレッタ [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/510jDW0RHIL._SL160_.jpg)