
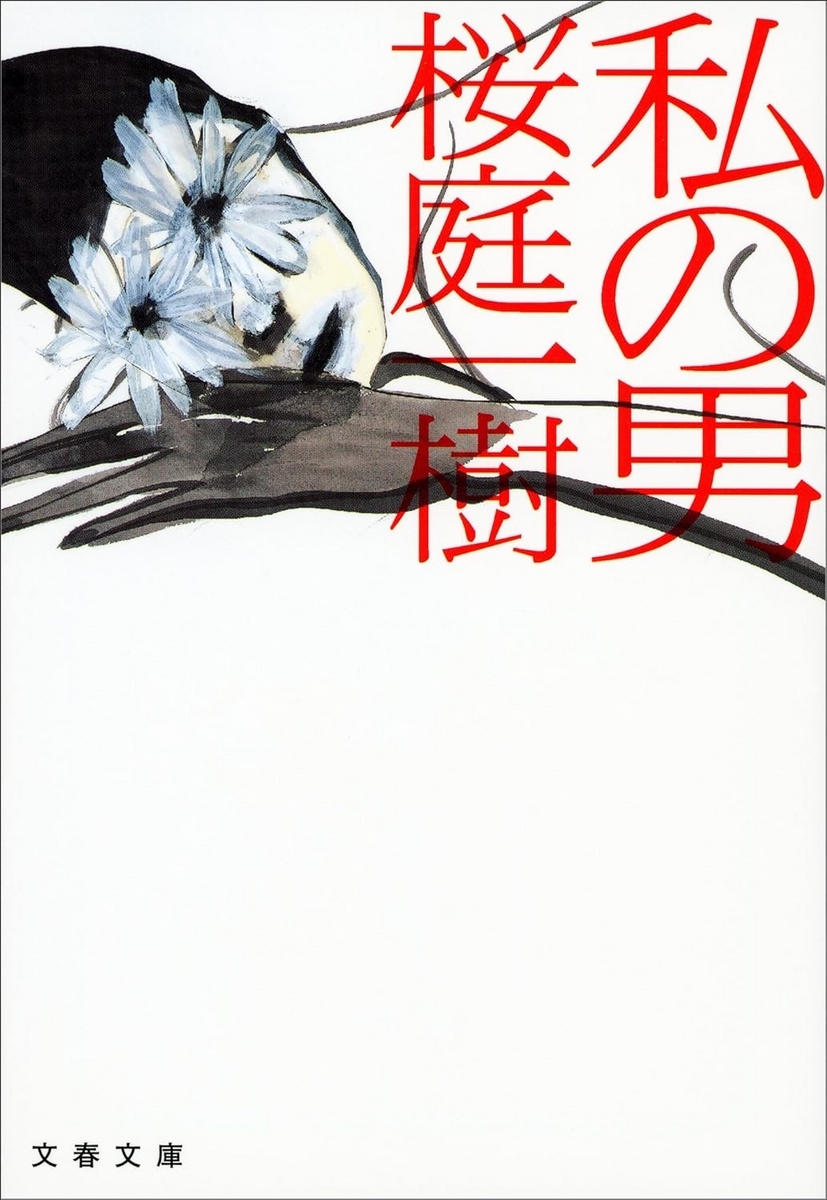 ≪内容≫
≪内容≫
落ちぶれた貴族のように、惨めでどこか優雅な男・淳悟は、腐野花の養父。孤児となった10歳の花を、若い淳悟が引き取り、親子となった。そして、物語は、アルバムを逆から捲るように、花の結婚から2人の過去へと遡る。内なる空虚を抱え、愛に飢えた親子が超えた禁忌を圧倒的な筆力で描く。
浅野忠信、二階堂ふみ主演で映画化。
この小説、すごく好きです。
私の親友は読書家ですが、この本に関してはどうしても意味が分からなくてページが進まなかった・・・と言っていました。
賛否両論、好き嫌いが分かれそうな作品ですが、私はとても好きです。
読むたびに結末が変わる小説。

最初に読んだのはまだ23歳くらいだったと思います。
その時も感動したんですが、今回は更に深く物語に入っていけたような気がします。
映画も見ていたからかもしれません。
映画版は二時間におさめなければいけないので、かなりポイントが絞られています。
そのためとても分かりやすいです。
ただ監督の解釈なので、自分の解釈と違うなら自分の解釈を信じるべき、と私は思っています。
小説も映画も答えはなくって、それはただ監督という一人の人間の解釈だからだと思っているからです。
特にこの小説は淳悟の心理描写がほとんどありません。
淳悟が口にする少しの言葉と、淳悟の周りの人間の言葉から、読み手が想像するしかありません。
映画版では、花の「絶対後悔したくない、好きな人にも後悔してほしくない」という気持ちと淳悟の「ずっと後悔している、俺は親父になりたいんだ」という擦れ違う心が軸になっていると感じました。
花は淳悟を愛しているから、淳悟の「親父になりたい」という願いを叶えるために、結婚し「私の男」から解放したのだと私は思っています。
最後の花が淳悟に向ける顔は「これで満足でしょう?」といったように見えます。
これが小説版だとすごく曖昧、というか色んな可能性があって答えがありません。
なぜ花と淳悟は離れなければならなかったのか。
淳悟はどこに行ってしまったのか。
家族とはなにか。
結末が希望なのか絶望なのか。
花にとって孤独の始まりなのか、今までと変わらない世界なのか。
この小説は読むたびに結末が変わるような気がするんですよ。
時に、淳悟は死んだ結末になり、海に帰った結末になり、時にひょこっと現れる結末になり、時に花の子供を可愛がるおじいちゃんになったりする気がするんです。
今回は死んでしまいました。淳悟は。
流しに近づくと、青くさくて、そのくせどろりとした臭気が漂ってきた。リボンに、見覚えがあった。披露宴の直後に、わたしから養父に渡した花束だ。茎と葉が無残に傷んで、緑と茶色を混ぜた色になり、花びらのほうも色をなくしてしおれていた。
青くさいような、泥水のような腐臭が強まってきた。
これが、家族の匂い・・・。
花にとって、この匂いは花を一人残して死んでしまった家族の匂いです。
淳悟が最後に残したこの匂いが何を意味するのか、そして花自身から匂う養父そっくりの雨の匂いは何を意味するのか・・・。
私には淳悟の肉体は消え、魂だけが花の中に留まったような、そんな気がするのです。
与えあう家族、奪いあう家族

養父と離れても、わたしからはあの、真っ黒な憎しみがあふれ続けていた。これからはいったい誰が、わたしからあふれるものを、奪ってくれるのだろう・・・。
/花
だけど、ほんとうは逆だったのかもしれない。
淳悟が、この子の、なにかをずっと奪っていたのかもしれない。形のないものを。大切なものを。魂のようなものを。
奪われて育ち、おおきな空洞に、なった。大人になって、奪って、生きのびる。あの人はそうなのかもしれない。
大人だけど、熟すことなく、腐るだけだ。
/小町
世の中には、けして、してはならんことがある。
子供にはわからんでも、大人が見本を見せんといかん。あの男も、あんたも、家族を知らんのだ。家族ってえのは、なにもあんなことをせんでも、いっしょにいられるもんなんだ。あれは人間じゃない。わしは見た。ありゃあ、獣のすることだ。
/大塩のおじいさん
「うん。血っていうのは、繋がってるから。だからもしも俺の子がいたら、そのからだの中に、親父もお袋も、俺が失くした大事なものが、ぜんぶある。・・・さいきんそう思うようになった」
/淳悟
四者四様の家族像があります。
私は、大塩のおじいさんの考えが一番近いかな、と思います。
淳悟の血は繋がっているという考えもあるにはありますが、どちらかというと血が繋がっていようがいまいが、生きるってことは個人の戦いだと思っているし、失くしたものは他人の中には見つけられないと思っています。
失くすことに関しては、村上春樹の作品に出てくる人物のように、たまに思いかえしたり、失くしたことに気付いたり、失くしてから気付いたりすることしか出来ないと思っています。
失くすということは、未来がないということだから。
そこで終わってしまったことだから。
花と淳悟は血のつながった親子です。
花の母親と淳悟がそういうことをしたんでしょうが、その描写や詳細は描かれていません。ただ花の父親も知っていたことや、二人の会話から、もしかしたら淳悟が無理矢理関係を持たせたのかもしれません。
花は震災孤児で一人生き残り体育館にいるところを淳悟に見つけられます。
それまでは父と母、兄と妹の5人家族でした。
ですが、父と母、まわりの大人の腫れものに触るような態度に家族と暮らしていながら、ほんとうの居場所を探していました。
自分の居場所はここではないのだ・・・と。
ある日津波が襲ってきて、住民は一斉に非難しました。
そのとき、初めてまともに父と花は会話をしました。
逃げる途中、母と妹が転び、父は駆けつけるためにおぶっていた花を走ってきた軽トラックの荷台に投げて「生きろ」と声をかけ去って行きました。
兄も自転車で走る途中家族に出会いました。
家族はほんとうの家族だけで丸まって海に呑まれていきました。
ほんとうの家族ではない花を残して。
恐らく、花にとっての父は淳悟ではなく、この血のつながらない「生きろ」と言った父なのだと思います。
最後の「がんばれ、生きろ、花」と言ってくれたやさしい顔の父。初めて父から愛を感じた瞬間の一瞬後に花の目に飛び込んできたのは、家族の輪から外された光景でした。
花の真っ黒な憎しみはここからずっと生まれ続けます。
もしも、淳悟が花の憎しみを奪うのではなく、花の憎しみを癒す養父であったなら、花は全く別の人生になっていただろうな、と思います。
大塩のおじいさんは、花の中にある孤独感なり疎外感を癒してあげたかったのだと思います。
花にとって、てっとり早いのは淳悟のような愛なのかもしれません。
ただただ自分だけに注がれる愛という無責任で独りよがりな愛情。
だけど、そういう愛って依存です。
花は養父と離れたら途方に暮れちゃっている。
依存は自立からもっとも遠い場所へ連れて行きます。
淳悟がそのことに気付いたのかは分かりません。
だけど、確実に親は子供より先に死ぬのです。
親が子供に向ける愛は、親なしでは生きていけないように育てるのではなく、一人でも生きていけるようにすることだと私は思っています。
「私が子供のころはこうだったから」と言って自分の子供にも同じ罰を与えたり、自分が奪われたものを同じように奪うことが教育だと思う人の話も聞きます。
だけど、「こう言われて私はすごく嫌だったから」と言って自分の子供には、自分とは違うものを与えたり、奪われたものを奪わないように育てる親もいます。
家族はそれくらい近い存在です。
嫌でもなんでも。距離的にも血的にも。
私はどちらが正しいとか、こうした方がいいというのは分かりません。
正直なところ、淳悟のように熟せずに生きている大人はたくさんいると思っているし、そういう人に「大人なんだから」とか「君は欠損家族で育ったからほんとうの家族を知らない」なんて大塩のおじいさんのようには言えません。
人が与えられるのは持っているものだけです。
私は後輩なり年下にはすごく優しくしてしまう・・・というか、自然に気をかけちゃうというか可愛がってしまうのですが、それは自分が年上の人にそうされてきたからだと思うのです。
だから私としては私が優しいんじゃなくて、私が周りの年上の人たちに優しさを与えられて育ったから、私もまた年下の人たちにそれを与えているだけのことなんです。
与えられたから、また別の人に与えることができる。
そうやって廻り巡らせていく。
与えられたことにしても、与えられなかったことにしても、それはその人自身の責任なのだろうか?と思うと、私は言葉に詰まってしまいます。
人間の本質なんて、5%くらいのもので、他は環境や家族関係や交友関係、金銭関係が作っていると思うから。
淳悟に対して大人たちは色んなことを言う、花に対してはすごく優しい顔をする。
もちろん年齢というのは大きいけれど、与えられずに大きくなった大人に対して冷たすぎやしないか、とも思ってしまう。
この年齢になって思いますが、世の中には一応大人という年齢になった人たちの中でも与えられるほどのものを与えられていない人間もいるし、未成年でも他人に与えられるくらいたくさんのものを与えられて育った人間がいます。
大塩のおじいさんの言っていることは正論です。
だけど、救うなら花だけではなく淳悟も救うべきだと思いました。
あのやり方では花から出来たばかりの家族である淳悟を奪うだけです。
大塩のおじいさんは花に家族を与えようとして、家族を奪ったのです。
与えることと奪うことはとても繊細なことだと感じました。
愛ってなんなんだろう、ってよく思います。
人に対する愛情ってどこから生まれて、どうやって育っていくのかな。
愛を与えたいと思っても、手に入れたいと思っても、その感覚を知らなければ、その目に見えないものを誰かに与えられたことがあるという自覚がなければ、苦しいと思う。
私が今までの人生で出逢ったことがある人で、記憶に残るのはこの苦しんでいる人たちなんです。もがいたり、あきらめたりしている姿がとても苦しそうで、寂しそうなんです。
不思議なのは、愛は目に見えないのに、愛に苦しんでいる姿は見えることです。
私はどうにかしたいと思うけど、いつも何も出来ない。何も伝えられない、何も与えらられない。
持っていると思っているのに、それを与えたいのに、受け取ってもらえない。
すごく些細なことで。
好きだから傍にいるのに、それだけなのに信じてもらえない。
常に一緒にいても浮気の心配をされたり、どこかに行くんじゃないかと疑われたり。私の時間や自由を奪うことでしか愛を信じられない人に、そんなことをしなくても愛は逃げないんだと伝えても、奪うことを止められない。
私から与えるものは全てブラックホールに飛ばされて、相手の中に留まるのは相手自身が奪ったものだけ。
そんな関係は苦しすぎる。
たぶん、その人の中に愛を容れるには一人じゃだめなんだと思います。
一人きりの力じゃ奪われていく内にミイラになっちゃう。
たくさんの人の愛が必要で、その人が奪う必要がないんだって思えるくらいじゃなきゃ気付けないのかもしれない。
相手が苦しいのも分かる。だけど一対一だと、どうしたって奪われ続ける方は身が持たない。だから花と淳悟のように奪い合いながら生きていくしかなくなっちゃう。奪わなくても在るのに。どうしたら見つけられるんだろう。「どうして分かんないのよ!」って責めるんじゃなくて「なんか、すぐ近くに落ちてたから拾ってみたよ」って相手が自分で気付いて拾えるような場所を見つけたい。
そしてその道の案内人になりたい。
与えるでも奪うでもなく、サポート出来るような人間になりたいと思う。
