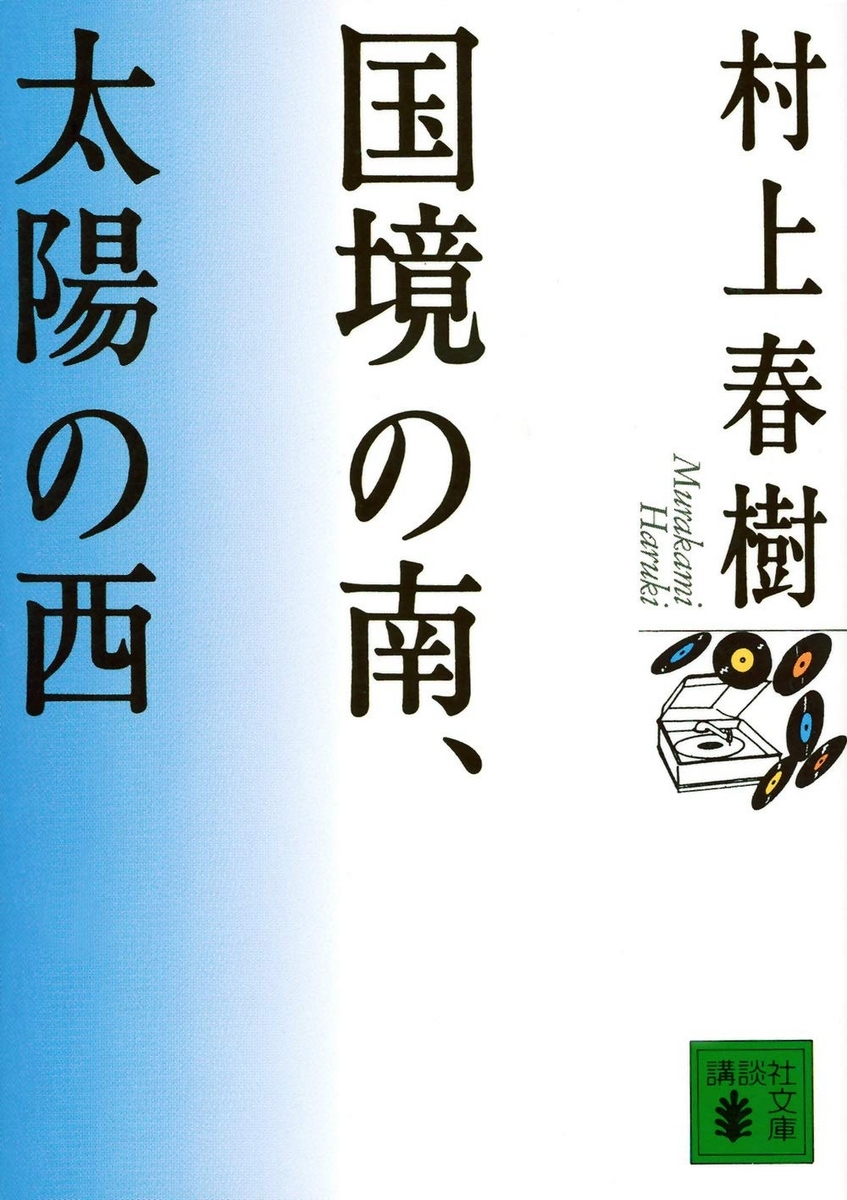 ≪内容≫
≪内容≫
今の僕という存在に何らかの意味を見いだそうとするなら、僕は力の及ぶかぎりその作業を続けていかなくてはならないだろう―たぶん。「ジャズを流す上品なバー」を経営する、絵に描いたように幸せな僕の前にかつて好きだった女性が現われて―。日常に潜む不安をみずみずしく描く話題作。
村上春樹の作品を「は?」って思える人って健全だと思う。
読み進めていった後半から、どんどん暗い底に向かって歩いているような感覚になりました。
落ちないように上に上に意識を落とさないようにしながら読み終わりました。
怖いです。
こんな作品を描き続けるには、そりゃあ肉体を健全に保たなきゃ呑み込まれちゃうよ・・・と思いました。
理想と現実

僕はもう孤独ではなかったけれど、それと同時にこれまで感じたことがないくらい深く孤独だった。
一人っ子の主人公は初めて出来た彼女とキスをし、こういった気持ちになりました。
私は姉がいる二人姉妹なので一人っ子の気持ちは分かりませんし、むしろノルウェイの森の緑のように一人っ子って親の愛情を独占出来ていいな、って気持ちがありました。
しかしこの一節を読むと、主人公は一人っ子だったからこそ他人との関わりに過度な期待があったんじゃないかなぁと思いました。
親とは違う同世代の人間との関わり。
それが濃密であればきっと孤独ではなくなるはず。
そう思っていたのに、肉体関係(キス)に至っても、特に何も変わるわけでもない。
自分が思い描いていた理想が崩れていくときの孤独。
そういったものを感じました。
理想と現実の埋め合わせをしていく内に理想は消えて現実だけで生きるしかないように思えてしまうけど、あらゆるどこでもない場所に理想は立っているんだと思う。
島本さんという幻想

幻想はもう僕を助けてはくれなかった。それはもう僕のために夢を紡ぎだしてはくれなかった。空白はどこまでいっても空白のままだった。僕はその空白の中に長いあいだ身を浸していた。その空白に自分の体を馴染ませようとした。
これが結局僕の辿り着いた場所なのだ、と思った。僕はそれに慣れなくてはならないのだ。
そしておそらく今度は、僕が誰かのために幻想を紡ぎだしていかなくてはならないのだろう。
本作品は結婚し娘も二人いて幸せを感じているはずの主人公が初恋の人である島本さんと出会い、家族や今の幸せより島本さんに心惹かれてしまう・・・というストーリーです。
ですが、島本さんは恐らく幻です。
主人公が都合良く作り出した幻とも言えるし、島本さんが主人公を救うために主人公への幻想を紡ぎだしたとも思えます。
幸せから生まれる悪があります。
主人公はやりたくもない教科書の校正という仕事から、結婚することによりジャズバーのオーナーになります。
それは主人公にとってやりがいのある楽しい仕事で、更にその仕事が成功し高級外車に乗り、高級ブランドの服を身に付け、義父から好きなだけ遊んでもいいという浮気の許し?も得て、遊びの浮気をし・・・とまぁ人から見たら「なんだコイツは!!」というような人間になっていきます。
こういう人間を勝ち組、やり手、成功者と感じ憧れる人もいると思うのですが、彼は個人の幸せとは裏腹に人間的にどんどん悪に染まっていきます。
主人公はどこかでこの悪に居心地の悪いものを感じているのですが、自分自身の力ではどうにも出来ない。
一度何かがうまくいかなくなる。するとそのうまくいかないことが別のうまくいかないことを生み出す。そして状況はどこまでも悪くなりつづける。どうあがいても、そこから抜け出すことができなくなってしまうのだ。誰かがやってきて、そこからひっぱりだしてくれるまで。
主人公はどんどん汚い世界に不本意ながら入っていきます。
それは結婚相手の父親の影響です。
妻は愛してる、子供も可愛い、だけど義父のやり方は好きじゃない。だけど家族が今のまま幸せに生きていくためには事を荒立てたくない・・・。
そういうふんづまりの状態にあった主人公をひっぱりだそうとしたのが島本さんです。
島本さんは一人っ子という点で自分と同じだったけれど、主人公のように器用ではありませんでした。
足が悪かったので生まれつき、人より出来ないことの方が多かった。
それは出来ないというより、他人に迷惑をかけたくないからしないという方が正しいのかもしれません。
主人公はそんな島本さんと一緒にいたころの自分に戻りたかったのだと思います。
悪の道に進む前の自分に戻りたい。
自分ではもうあの頃の自分を思い出せないけれど、島本さんがいてくれたら、なりたい自分になれる。
そういう強い欲から生まれたんじゃないかなぁ・・・と思います。島本さんの幻想は。
悪のはじまりはどこから?

しかし相手を愛しているとかいないとかいうのは、そのときの僕にとっては大事な問題ではなかった。大事だったのは、自分が今、何かに激しく巻きこまれていて、その何かの中には僕にとって重要なものが含まれているはずだ、ということだった。
それが何であるのかを僕は知りたかった。
とても知りたかった。
できることなら彼女の肉体の中に手を突っ込んで、その何かに直接触れたいとさえ思った。
初めての彼女を好きでいながら、その彼女の従姉と何カ月も何十回も寝ているときに主人公はこんなことを思っていました。
彼女の従姉とは別に愛し合っているわけではない、だけど寝る。
彼女は大好きで大切だけど、従姉とは寝る。
なぜなら、そこに潜む悪に触れたいと思ったから。
羊シリーズの鼠とは違う道を選んだ話ですね。
いや、もしかしたらこの先は鼠と同じ道を辿るのかもしれない。
だけど、主人公は悪に魅了され、悪に苦しめられ、逃れられず足掻きながらも、妻や子供の存在によって死から免れます。
まだ国境の南と太陽の西の中間あたりにいるんじゃないですかね。たぶん。
中間はないの、と島本さんは言います。
私の中には中間的なものは存在しないし、中間的なものが存在しないところには、中間もまた存在しないの。
はたして中間とは?
中間的なものが存在するからあるもの?
中間があるから中間的なものが存在するのか?
国境の南と太陽の西とは理想に向かう入口と、理想が絶望に変わった出口みたいなものなんじゃないかなぁと思います。
思えばダンスダンスダンスでは
世界は後味の悪い不条理な死で満ちていた。僕は無力であり、そして世界の汚物にまみれていた。人々は入口から入ってきて、出口から出ていった。出ていった人間は二度と戻ってこなかった。
出口から出ていった人間は二度と戻ってこないし、島本さんは僕のように世界の汚物にまみれるということは絶対にない。
ということは、社会に出る前の世界か死しかないということにならないか?と私は考えます。
社会というのは汚物にまみれています。
まみれない人間なんていないし、まみれていないというなら別の誰かがあなたの代わりにまみれているのだと思っていい。
私たちは中間で生きるしかないと思うんですよ。
これは厭世感でもなくて、真実としてそう思うのです。
何かいいことがあって「めっちゃ嬉しい!」と最高潮のハッピーテンションで生きる私の一日の反対側では誰かが戦争で殺されているかもしれないんです。
誰かの死の上に私が存在してるとは思わない。
だけど、この世界は絶対に綺麗なことだけでは機能していない。
村上春樹のいうシステムというのは、私の中で社会であり、社会が生まれたのはヒトが動物から人間へと変貌するためです。
理想と現実の中間でしか生きることは出来ないんです。
それが理想に偏ってもダメだし、現実に偏ってもダメで、どちらかに偏ると生か死か、とか精神を病んだりすると思います。
もう最後の方読んでて辛かったー・・・。
読み手も健全な肉体を持っていないとダメだこりゃあ。
たぶん。



