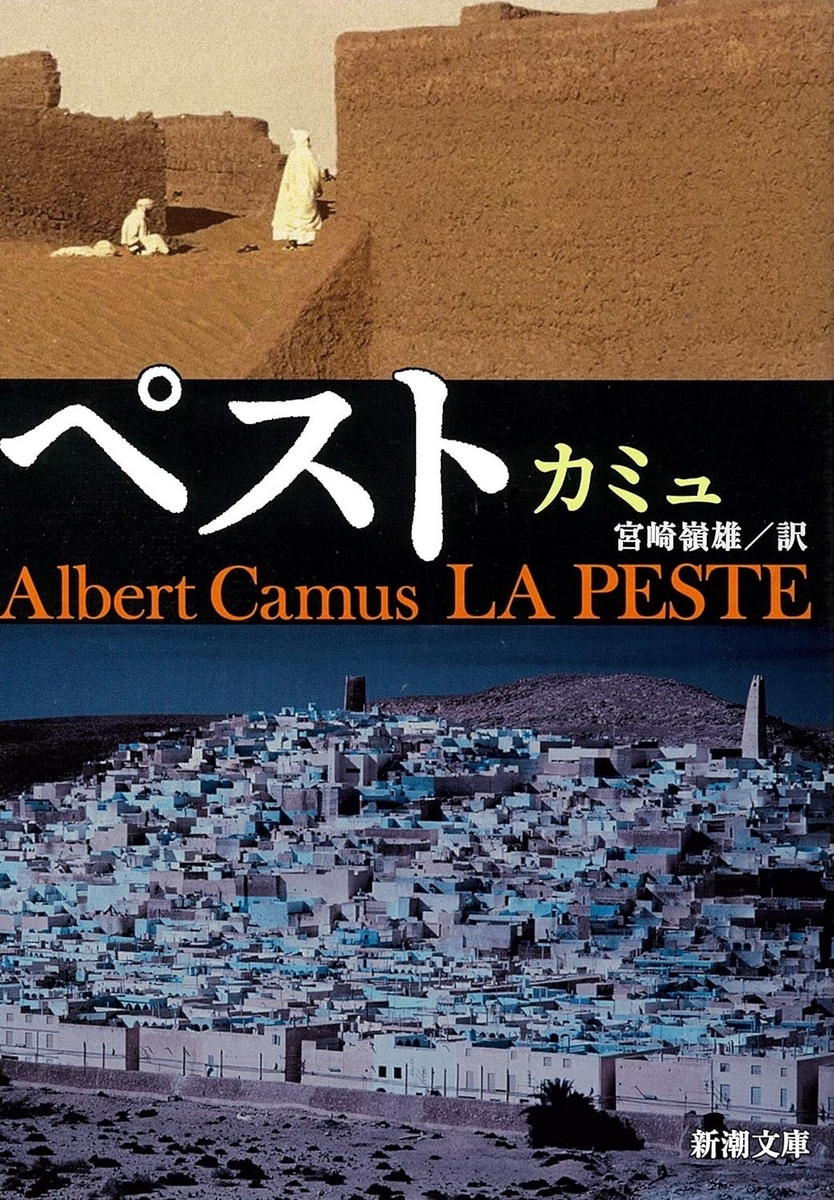アルジェリアのオラン市で、ある朝、医師のリウーは鼠の死体をいくつか発見する。ついで原因不明の熱病者が続出、ペストの発生である。外部と遮断された孤立状態のなかで、必死に「悪」と闘う市民たちの姿を年代記風に淡々と描くことで、人間性を蝕む「不条理」と直面した時に示される人間の諸相や、過ぎ去ったばかりの対ナチス闘争での体験を寓意的に描き込み圧倒的共感を呼んだ長編。
カミュといえば「不条理の哲学」なんですね。
初めて知りました。というか初めてカミュを読みました。
これね、現代で分かる人ってかなり限られる気がしますが、どうなんでしょう?
発売当時の誰もが戦争という不条理な戦いの中にいた時代なら、この作品の「不条理」に対して共感なり感じると思うんですが。
今って国全体で、皆で何かに巻き込まれることってないじゃないですか。
だから、私はこの小説を読んで言わんとしてることは分かるけど奥深くまで突き進めなかったこと自体が「平和」を意味しているんじゃないかなぁと思いました。
あと、やっぱり昔の海外小説って読みづらい・・・。私だけ?
真の善良さ

しかし、筆者はむしろ、美しい行為に過大の重要さを認めることは、結局、関節の力強い賛辞を悪にささげることになると、信じたいのである。なぜなら、そうなると、美しい行為がそれほどの価値をもつのは、それがまれであり、そして悪意と冷淡こそ人間の行為においてはるかに頻繁な原動力であるためにほかならないと推定することも許される。
いよいよペストが蔓延し、無視できないほど被害が拡大していきました。
そこで保険隊を作ったリウーはこう考えます。
保険隊を実際以上に重要視して考えるつもりはないと。
国民はすでにペストが他の国で猛威を奮ってきた事実を知っています。なので、罹患者に関わるということは、感染に近い、死ぬ可能性が大きいということを理解しています。ですから、わざわざそんな前線に立とうとする者を誇張したいとは思うが、彼らを讃えることはペストの強力さへの服従とも思われます。
私は「ペスト」っていうタイトルから、ペストの話だと思っていたんですが、ペストはただの手段にしか過ぎず、これは、戦争でも天然痘でも成り立ちます。
書かれていることは、それぞれの道徳や考え方です。
無知の涙という死刑囚が書いた本があります。もし彼が教育を受けていたら、知識を得られる環境にいたなら・・・。
ペストにおいて無知はこう書かれています。
世間に存在する悪は、ほとんど常に無知に由来するものであり、善き意思も、豊かな知識がなければ、悪意と同じくらい多くの被害を与えることがありうる。
ペストという有名でありながら、治療方法の見つかっていない災厄に襲われたとき、人は無知ゆえに、善と悪の判断がつかなくなってしまうかもしれない。
日常では許されていない殺人も、感染源が分からない恐怖にかられて罹患者は殺してもよいのだと認めてしまう。
善きことを行っているつもりで悪に跪いているということは、無知ゆえに世間に存在し続ける。
ペストを歓迎した者

彼の欲しない唯一のことは、つまりほかの人々から引き離されないことである。彼としては、みんなと一緒に襲われているほうが、一人ぼっちで囚われの身となっているよりましなのだ。
こういう考えを持つ人もいるのね・・・としみじみ思ってしまいました。
大半の人は自分はもちろん恋人や家族など愛する人がペストに罹らないことを願うし、早くペストが消滅あるいは有効な治療法が生まれるのを待っています。
国が閉鎖されてからは故郷に戻れなくなった旅人や、故郷に帰れなくなった者は、突然の別れ(しかも死に目にも会えない)に悲しみに暮れるだけしか出来ません。
誰もがペストから逃れようとしている中で、ペストと共謀する者もいる。
一人で戦っている人がいるなんて普段の生活からは分かりません。誰にでも家族や恋人や親友、親しい友達やただの友人、職場の人がいて。それぞれが自分の人生を歩いているし、それが当たり前だと思っている。
どこかに誰かと一緒に戦いたいと思っている人間がいたとしても気付くことはほぼ不可能だと思う。
誰もが自分の生活や、自分の手の届く相手にしか目がいかないし、それで自分の人生は成り立つから。
団結するには何か大きな敵を作るのがいいと言いますが、まさにこのことかなぁと思います。団結というとちょっと違いますが、満員電車とかライブのぎっしり密集した感じって、自分が空虚なときほど受け入れられるものです。
何か目標があったり、前進したいとき、上手くいかなくてイライラしているときなんかは最悪に感じますが、行き先が分からないときは顔も性格も何にも知らない他人たちに中にいるというのは変な安心があるんですよね。
ペストってペスト(病)の話じゃないな。
人を人としてみること

ところが、この日のことについて、僕の心にはたった一つのイメージが残っただけだ。それはその罪人のイメージだった。
僕はその男が有罪だったと信じているし、それがどんな罪だったかはたいした問題じゃない。
しかし、その小柄な、年は三十くらいの、貧弱な赤毛の男は、何もかも認めようとすっかり決心している様子で、自分のしたことと、これから自分に対してされようとしていることに、すっかり心からおびえている様子で・・・(中略)
要するに、くどくいわないでもわかっただろうか。
この男は生きていたのだ。
検事である親爺の裁判を見ていたときのこと。
それまでは「容疑者」としてしか見ていなかったが、彼は突然この男(容疑者)が生きていることに気付く。
彼は言います。
僕はこの町や今度の疫病に出くわすずっと前から、すでにペストに苦しめられていたんだ。
ペストっていうのは「無知」のことなんだと思います。
最初に書いたように、無知ゆえに自分が他人を殺す決断をするに値する人間であると思いこみ信じること。
それを疑問にも思わず賛成する人々。
彼らにとって罹患者は人間ではなく「罹患者」であり、他には何もないのです。
そして、容疑者は「容疑者」であり、人間ではないのです。
このことは善きことなのだろうか?
ペストは悪。容疑者も悪。では裁くものは善なのか?
何が善で悪なのだろうか?
世の中のどれくらいの人が、他人に対して「生きている」と思っているだろう?と思う。芸能人だから誹謗中傷していい、悪質なコメントを残しても血は流れないから傷付けている実感も薄い。
それって相手を「生きている」人間として考えられているのかな?
本書の中で一番響いたのはここのシーンです。
人が人の命を決めていいのか。
人の命を奪ったものの命を奪うことを、私たちが決めていいのか。
死刑制度反対の概念はここにあるのか?
犯罪者の人権を奪っていいというのは、私たちが決めていいのか。
あ~もう分からない、、、
特に、本書はキリスト教の説教も出てくるのですが、それもう~ん、、、どうなの?って思ったり、でも今の医療の中で生きているから疑問に思うのであって、当時だったら信じるかも・・・とか思ったり。
ペストって出来事としては、伝染病のペストなんですけど精神的には善悪の話に感じました。
不条理の哲学の話という説も見たのですが、不条理っていうのがちょっとピンと来ないのでいまいち分かりません。
それに関しては「シーシュポスの神話」を読んでみたいと思います。
なんか、私、ちゃんと他人のこと「生きている人間」として見れているのか不安になりました。死なないのが当たり前だと、なんだか傷をとっても軽く感じてしまいます。難しいけど、人の痛みとか傷を鮮明に想像出来たら、もっと生身であることのか弱さを強く感じられるのかなぁと思いました。
誰かが死んでから気付くのはいやだ。